�� �ȤŤ���Ʀ�μ�
���ư�ͷ��ƽ������Ƥ褦�ȷײ褵��Ƥ��������ء��ȤŤ���Υݥ���Ȥ�ʷ�ˤޤȤ�Ƥߤޤ�����
����ơ��ȤŤ�����¤������Ǥ��ä��졢�ȤŤ����ڤ����ĺ�����鹬���Ǥ���
�ȤŤ���˿����˸����礤�����ä���ȲȤŤ���������ݡ��Ȥ��ޤ���
�����˵��ܤ����Ƥϡ��ϰ��ˡ���β������ˤ��ۤʤ��礬����ޤ���
���ϰ��ǿ��ξ���ˤĤ��Ƥ⤦�����ܤ����Τꤿ�����ϡ����ե������ˤƤ����ڤˤ����̲�������
�����̤�̵���Ǥ�������
|
E. �Ѹ������ |
���۴��ˡ�������ƻϩ�פȤϡ�����4���ʾ�Τ�Τ�����ޤ���
â����ƻϩ����6�����������ģ�����ꤷ�����ϡ�4����6�����֤������ƹͤ���ɬ�פ�����ޤ���
����ƻϩ������ʷ��۴��ˡ42��1��1���5���
|
ƻϩ�μ��� |
��� |
|
��1��� |
ƻϩˡ�ˤ��ƻϩ�ǡ���ƻ����ƻ�ܸ�ƻ����Į¼ƻ�ʤɤθ�ƻ |
|
��2��� |
�ԻԷײ�ˡ�����϶������ˡ���ԻԺƳ�ȯˡ�ʤɤ�ˡΧ�˴�Ť����ȡ��ԻԷײ���Ȥʤɡˤˤ�ä���¤���줿ƻϩ |
|
��3��� |
���۴��ˡ��3�Ϥε��꤬Ŭ�Ѥ�����1950ǯ�˰�������¸�ߤ���4����6������6���˰ʾ�θ�ƻ�ޤ��ϻ�ƻ�ǡ����¤˰��̸��̤��Ѥ˶����Ƥ����� |
|
��4��� |
ƻϩˡ�ʤɤ�ˡΧ�ˤ�ꡢ���ߤޤ����ѹ��λ��ȷײ�Τ���ƻϩ�ǡ�2ǯ����ˤ��λ��Ȥ����Ԥ����ͽ��Τ�ΤȤ��ơ��������ģ�����ꤷ����� |
|
��5��� |
���ֻ���ƻϩ�ȸ���������δ���Ŭ�礷���������ģ������֤λ�����������ʬ���Ϥʤɤǡ˿�������ȯ���줿��ƻ |
�ԻԷײ�ˡ�������ԻԷײ���ʤɡ����ڷײ���γ�ά���������ޤ���
�����������
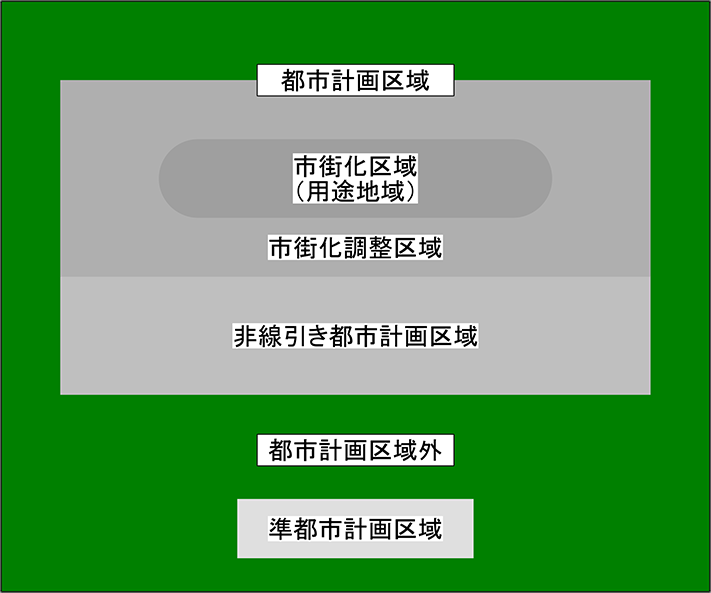
�����ԻԷײ���
��Į¼���濴�Գ��Ϥ�ޤߡ����ġ�����Ū���Ҳ�Ū�������������ѡ������̡��ԻԻ��ߤ����֤ʤɤθ�
���ڤӿ�ܤƤ��ơ����Τ��ԻԤȤ�������Ū����������ȯ����������ɬ�פ����������ƻ�ܸ�������
�����ΤǤ���
�����Գ������
�����23����ʤɡˤ��Ǥ˻Գ��Ϥ�������Ƥ�����ڤӡ��������10ǯ�����ͥ��Ū���ķײ�Ū�˻Գ���
��ޤ�٤����ǡ������ϰ褬�����Ƥ��ޤ���
�ԻԻ��ߤȤ��ơ�ƻϩ�����ࡢ����ƻ�ʤɤ������Ƥ��ꡢ��������������Ū�˹Ԥ��Ƥ��ޤ���
�����Գ���Ĵ�����
�Գ������������٤����ǡ������ϰ���ԻԴ��פ������ϡ�����Ū�˹Ԥ��ޤ���
�������������ԻԷײ���
�Գ������ڤӻԳ���Ĵ�����˶�ʬ����Ƥ��ʤ��ԻԷײ���Ǥ���
�������ԻԷײ���
�ԻԷײ��賰�Ρʹ�®ƻϩ�Υ����������ա�����ƻϩ�α�ƻ����¸����μ��դʤɤΡ˹ٳ��ʤɤ�
����ȯ�ٵڤӷ��۹٤����ä������Ӥ�̵����ʺ��ߤʤɤǡ��������Ѿ�����꤬ȯ�����ʤ��ͤˡ��ԻԷ�
�ײ���˽स��������ǧ������٤Ǥ���
���������ϰ�
���Ķ����ݸ���ꡢ���Ȥ乩�Ȥ����ؤ����ʤ��뤳�Ȥ���Ū�Ȥ��ơ��ԻԷײ�ˡ�ǡ�������13���������
�ϰ�����ơ����۴��ˡ�ǡ������ϰ�˷��ۤǤ������ʪ�����¤����ΤǤ���
�����ϰ�ϡ��Գ������ˤ�ɬ�������ޤ��������������ԻԷײ��衢��ȯ���Ĥ�������Գ���Ĵ�����
�����ԻԷײ���ʤɤǤ��������礬����ޤ���
|
�����ϰ� |
���� |
|
�������ؽ��������ϰ� |
����ؤ�����˳ع���Ź��ʻ�ѽ���⤢��ޤ�������3�����ƤޤǤΡ����ؽ����濴���ϰ�Ǥ� |
|
��������ؽ��������ϰ� |
�������ؽ��������ϰ�˲ä��ơ��ʥ���ӥˤʤɤΡ˾����Ϥ�Ź�ޤ����۲�ǽ���ϰ�Ǥ� |
|
��������ؽ��������ϰ� |
��ء��±���500�ְʲ���Ź�ޤ⤢��ޤ������ʥޥ��ʤɤΡ�����ؽ����濴���ϰ�Ǥ� |
|
���������ؽ��������ϰ� |
��������ؽ��������ϰ�˽स��Ź�ޤε��Ϥ�1,500�ְʲ��ޤǷ��۲�ǽ���ϰ�Ǥ� |
|
���サ���ϰ� |
Ź�ޤ�¾���ܡ���졢�ۥƥ�ʤɤε��Ϥ�3,000�ְʲ��ޤǷ��۲�ǽ���ϰ�Ǥ� |
|
����サ���ϰ� |
���サ���ϰ�˲ä��ơ��ѥ���Ź�䥫�饪���ܥå����ʤɤθ�ڻ��ߤ����۲�ǽ���ϰ�Ǥ� |
|
�ཻ���ϰ� |
������̤�褤�ˤ��ꡢ����ȡ���־졢�������硼�롼��ʤɤΡ˼�ư�ִ�Ϣ���ߤ���¸���Ƥ����ϰ�Ǥ� |
|
�ıཻ���ϰ� |
���Ȥ����ؤ����ʤ�ޤ�Ĥġ������Ĵ�¤������ؽ�����ɹ��ʴĶ����ݸ�뤿����ϰ�Ǥ� |
|
���پ����ϰ� |
���ٽ�̱�ΰ٤�Ź�ޡ���̳���濴���ϰ�Ǥ� |
|
�����ϰ� |
���پ����ϰ�˲ä��ơ��絬�ϤʱDz�ۡ��ǥѡ��ȡ���̳��ʤɤ����ؤ����ʤ�ޤ��ϰ�Ǥ� |
|
����ϰ� |
�Ķ��ΰ�����⤿�餹����Τʤ������濴���ϰ�Ǥ� |
|
�����ϰ� |
�ع����±������Ƥ��ʤ������濴���ϰ�Ǥ� |
|
���������ϰ� |
�����ϰ�˲ä��ơ�ͣ�콻�𤬷��Ƥ��ʤ������濴���ϰ�Ǥ� |
�Գ��Ϥˤ�����кҤδ������ɤ��٤ˡ��ԻԷײ�ˡ�ǡ��ɲ��ϰ�ڤӽ��ɲ��ϰ褬���ꤵ��Ƥ��ޤ���
�ޤ����������ģ�ϡ��ɲ��ϰ衢���ɲ��ϰ�ʳ��λԳ��ϤˤĤ��ơ����۴��ˡ22���Ŭ�Ѥ���٤��ϰ�
���̾Ρ�ˡ22����ˤ���ꤹ���礬����ޤ���
����Գ��Ϥ��ɲдط��ϰ襤�����
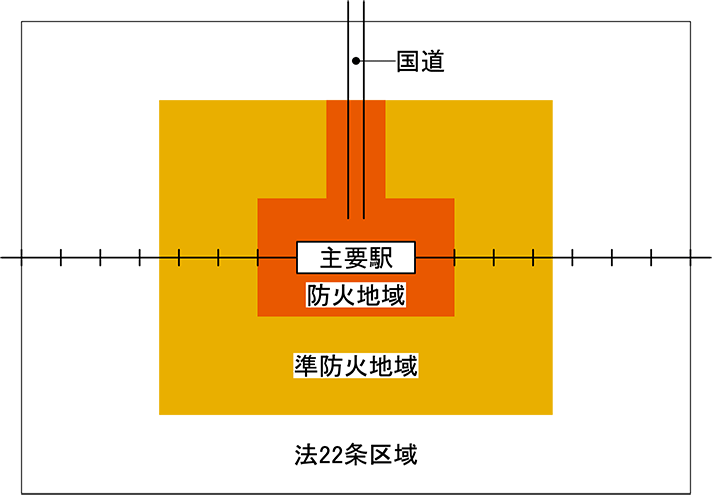
�㤨�С����23��ϡ���ʪ��̩�����Ƥ����ϰ褬¿�����кҤ��ﳲ������䤹���Τǡ����Ƥ��ɲ��ϰ�ޤ�
�Ͻ��ɲ��ϰ�˻��ꤵ��Ƥ��ޤ���
���줾����ϰ�ˤ��������ʪ�ؤζ���Ū�����¤ϡ����۴��ˡ�ڤ�Ʊˡ�ܹ���ˤ�ä������Ƥ��ޤ���
�����ɲ��ϰ�
�ԻԤ��濴�Գ��ϡ����������׳�ϩ�褤�ʤɤǡ����Ȼ��ߤ�ӥ뤬̩�����Ƥ����ϰ褬���ꤵ��ޤ���
����ʪ�ϡ��⤤�ɲ���ǽ������졢�ϳ���ޤ೬����3�ʾ����ϡ������˴ط��ʤ���������ѡ�S�ˤ�100
�֤�Ķ�������ʪ�ϡ��Ѳз���ʪ���Ȥ��ʤ���Фʤ�ޤ���
�����ɲ��ϰ���η������¡�
|
�������ϳ���ޤ�� |
S��100�� |
S��100�� |
|
3�ʾ� |
|
|
|
2 |
�Ѳз���ʪ���� |
�Ѳз���ʪ�� |
|
1 |
���Ѳз���ʪ�� |
|
�������ɲ��ϰ�
�ɲ��ϰ�γ�¦�ǡ��ɲ��ϰ�˼����Ƿ���ʪ��¿���ϰ褬���ꤵ��ޤ���
����ʪ�ϡ��ɲ��ϰ�˼����ǹ⤤�ɲ���ǽ������졢�ϳ������������4�ʾ�ޤ��ϡ������˴ط��ʤ�����
�����ѡ�S�ˤ�1,500�֤�Ķ�������ʪ�ϡ��Ѳз���ʪ���Ȥ��ʤ���Фʤ�ޤ���
��
������ɲ��ϰ���η������¡�
|
�������ϳ�������� |
S��500�� |
500�֡�S��1,500�� |
S��1,500�� |
|
4�ʾ� |
|
|
|
|
3 |
�Ѳз���ʪ�����Ѳз���ʪ�������ɲо�ɬ�פʵ��Ѵ���Ŭ�礹�����ʪ |
�Ѳз���ʪ���� |
�Ѳз���ʪ�� |
|
2 |
���¤ʤ� â������¤����ʪ�ʤɤdz��ɡ����α�ƤΤ��� |
���Ѳз���ʪ�� |
|
|
1 |
��Τ�����ʬ���ɲй�¤ |
|
|
��
����ˡ22����
ˡ22����ϡ��ɲ��ϰ衢���ɲ��ϰ�Ȥϰۤʤꡢ�ԻԷײ��賰�Ǥ��äƤ���ꤹ����ϲ�ǽ�ȤʤäƤ�
�ޤ���
�ֲ�����dz���פȤ�ƤФ졢����ʪ�β�������dz��������������¤����ʪ�γ��ɤ���ƤΤ�����Τ�����ʬ
����ɲй�¤�ʾ�ˤ��ʤ���Фʤ�ޤ���
�ܼ��������
�ַ���ʪ�פȤϡ����Ϥ����夹�빩��ʪ��E-005. ���Ϥ����夹�빩��ʪ�Ȥ����ȡˤǡ����˵��Τ��
���ޤ���
1. ���������ꡢ����ɤ�ͭ������
2. 1����°�������ʽ
3. �����ΰ٤ι���ʪ�ʲ�����̵������䶥�Ͼ��ޤ��
4. �ϲ����Ϲ�ͤι���ʪ����ߤ�����ߡ��ϲ���Ź������̳�ꡢŹ�ޡ��Ҹˡ��ƥ�����Ÿ˾������
5.��1��4�η���������E-006. ���������Ȥ����ȡ�
�����ʪ�ȤϤʤ�ʤ���Ρ�
1.��Ŵƻ�ڤӵ�ƻ����ϩ������ˤ��뱿ž�ݰ¤˴ؤ�����ߡʿ�����ߡ�Ƨ���־�������
���ؼˤϷ���ʪ�Ǥ���
2.��Ŵƻ�ڤӵ�ƻ�θ��������ץ�åȥۡ���ξ岰
3.����¢��ʥ������ˡ�����������
�����Ϥ����夹�빩��ʪ�פȤϡ�����ʪ��E-004. ����ʪ�Ȥ����ȡˡ��硢ʽ�����졢�ȥ�ͥ������Ͼ�����
��������֤��줿��Τ�����ޤ���
������Ǥ⡢�����Τ褦�˳�ǧ������ɬ�פʹ���ʪ�Ȥ��ơ����۴��ˡ��Ʊ�ܹ���ǻ��ꤵ��Ƥ��빩��ʪ��
����ޤ���
1.�����͡ʹ⤵��6���ˡ������������ȡ����Ѥ����
2.���ң�¤���졢Ŵ�졢�������ʹ⤵��15���ˡ������������ȡ��Ͷ�����ϩ���������
3.�������㡢�����ġ������㡢��ǰ�����ʹ⤵��4����
4.����Ϳ��塢��������ʪ�������ʹ⤵��8����
5.���������ʹ⤵��2����
6.���Ѹ��Ѥξ��ߵ��ʴѸ��ѥ���١��������Ѹ��ѥ������졼�����ˡ������������̸����ѤϷ��������Ȥ���
����
7.����ͤ�ͷ�����ߡʥ������������������������塼������
8.����ư���ղ�žͷ�����ߡʥ��������ɡ������֡�����������
9.����¤���ߡ���¢���ߡʥ���ȥץ�������
10.����ư�ָּˡʵ��������Dz�����̵����Ρ������̤���ι⤵��8����
11.����ʪ�����졢���߾ƵѾ���
�ַ��������פȤϡ�����ʪ��E-004. ����ʪ�Ȥ����ȡˤ��ߤ��뼡�˵��Τ�����ޤ���
1.���ŵ��ʢ�1�ˡ����������ӿ塢����������˼����ʪ������������Ǣ����������
2.���òСʥ��ץ�顼���ˡ��ӱ�
3.�����͡ʢ�2�ˡ����ߵ��������
�����η��������ϡַ���ʪ�פ�����˴ޤޤ�Ƥ��ޤ���
�ʢ�1�˷���ʪ�β���ˡ����η���ʪ���ŵ��뤹��٤����֤�����������ȯ��������ޤߤޤ���
�ʢ�2�˸������������Ω�������ͤϹ���ʪ�ǤϤ��뤬�����������ǤϤ���ޤ���
�ַ��ۡפȤϡ�����ʪ��E-004. ����ʪ�Ȥ����ȡˤ��ۡ����ۡ����ۡ���ž�����������ޤ���
1.������
�������ʪ�η��äƤ��ʤ����ϡʹ��ϡˤ˷���ʪ����Ƥ���Ǥ���
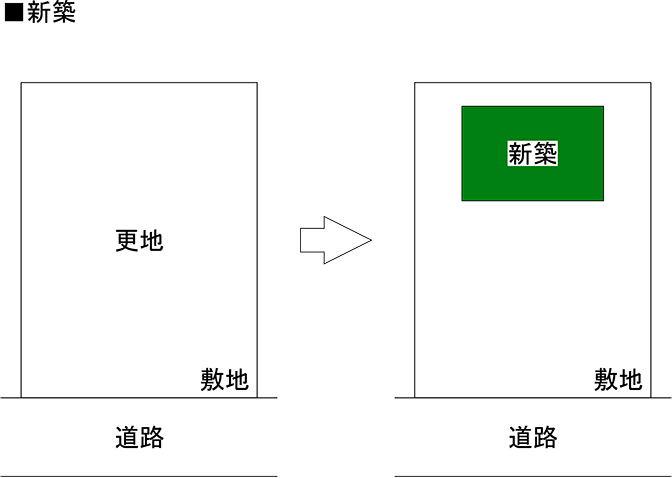
2.������
������˴�¸����ʪ�����ꡢ�����˷���ʪ����������Ǥ���
��³���ξ��ȡ�����ξ�礬����ޤ���
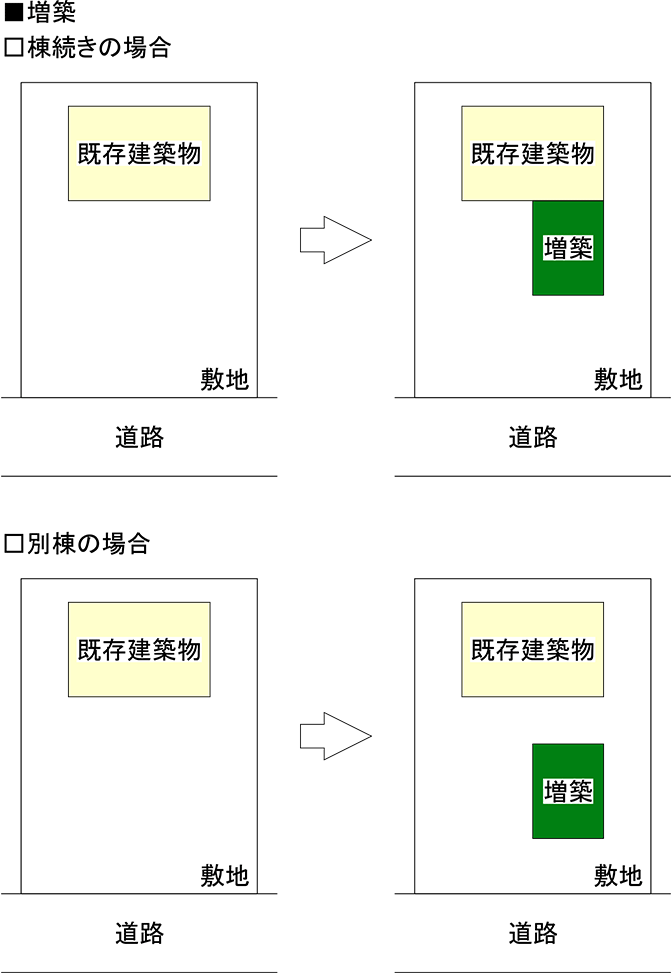
3.������
�����η���ʪ��������ơ����֡���¤�����ϡ����Ӥ��ۤ�Ʊ������ʪ�����ľ�����Ǥ���
�ҳ���η���ľ����ޤޤ�ޤ���
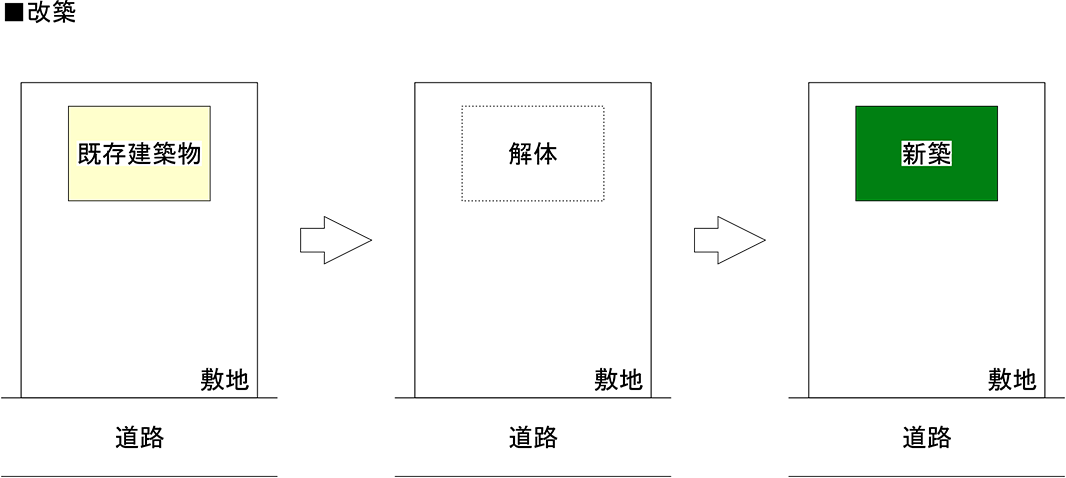
4.����ž
Ʊ��������ˤ����ơ�����ʪ���ư�ʱȲȡˤ�����Ǥ���
�̤����Ϥذ�ž�������ϡ��������ϤˤĤ��ƿ����������ۡʴ�¸����ʪ��������ˤȤʤ�ޤ���
���ߤˡ���¸��Ŭ�ʷ���ʪ��C-019. ��¸��Ŭ�ʷ���ʪ�Ȱ�ȿ����ʪ�ˤĤ������ȡˤˤ����Ƥ�Ʊ���������
���Τޤް�ž������ϲ�ǽ�Ǥ���
�ޤ����̤����Ϥذ�ž������ˤ����Ƥ⡢���̡��������ɲС���������ڤӻԳ��ϤδĶ�������پ㤬
̵�����������ģ��ǧ�����ϡ����Τޤް�ư����ǽ�Ǥ���
â��������Ψ������Ψ���ν��ĵ���ˤĤ��Ƥϡ���§����ư��δ�बŬ�Ѥ���ޤ���
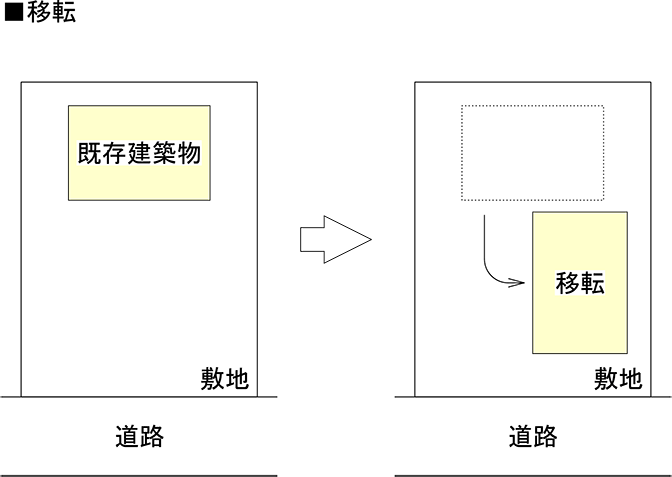
E-008. �絬�Ϥν������絬�Ϥ������ؤȤ�
1.���絬�Ϥν���
����ʪ������¤���ΰ��ʾ�ˤĤ��ƹԤ���Ⱦ�ν����λ��Ǥ���
��¸�Τ�ΤȤ������Ʊ����������ˡ�������˸���٤˹Ԥ��빩�������ȸ����ޤ���
2.���絬�Ϥ�������
����ʪ�μ���¤���ΰ��ʾ�ˤĤ��ƹԤ���Ⱦ�������ؤλ��Ǥ���
��¸�Τ�ΤȤ������Ʊ����������ˡ�ǡ��ۤʤ������������˸���٤˹Ԥ��빩���������ؤȸ�����
����
���絬�Ϥν������絬�Ϥ������ؤˤʤ�ʤ���������
������¤�������ʾ�ˤ錄�äƤ⡢���μ��त����ˤĤ��Ƥ��Ⱦ�ʢ��ˤˤʤ�ʤ����
�ʢ��ˡֲ�Ⱦ�פȤϡ��̾�����ȤǤϤʤ�����η���ʪ���ΤˤĤ��Ƥν����������ؤ����¤���γ�
��ˤĤ��Ƥ�ؤ��ޤ������������ģ�ˤ�äư������ۤʤ��礬����Τǡ�ǰ�ΰ١�������������ģ�˳�
ǧ���������ɤ��Ǥ���
�����������ࡢ���ɤγ���������ƤϽ�����������Ǯ�ࡢ���С���ˡ�Τߤβ���������6.2.8��355��
������¤���Ǥʤ��ֻ��ڤ��ɤ䲰�����ʤ����Ƽ�괹��
�����Ѳз���ʪ
����¤���Τ������ɲо�ڤ������پ㤬�ʤ���ΤȤ��������������ʬ�ʳ�����ʬ���������¤����
���Ѳй�¤�����Ѳ���ǽ�δ���Ŭ�礷����ΤȤ������ɤγ���������ƤΤ�����Τ�����ʬ���ɲ���������
���Ƥ����ΤǤ���
Ŵ�ڥ����¤��RC¤������Ŵ��¤��S¤�ˤ�����Ū�Ǥ���
��¤�Ǥ���ڸ�����ä�ǧ����������Τ⤢�ꡢ���㤬���ä��Ƥ��Ƥ��ޤ���
�������Ѳз���ʪ
�Ѳз���ʪ�˼������Ѳ���ǽ�θ��������������ꡢ������3�Ĥδ�ब����ޤ���
Ŵ��¤��S¤��������¤������Ū�Ǥ���
������-1��1���ֽ��ѲСˤȥ�����-2��45ʬ���ѲСˤ�����ޤ���
��¤3������Ʊ����ʤɤϥ�����-1������Ū�ʽ���Ǥϥ�����-2�δ��Ȥʤ�ޤ���
���οޤϥ�����-2��45ʬ���ѲСˤ��ޤ���
��1.�������ѡ�������������¤�����Ѳй�¤�ʷ��۴��ˡ��2��9���3����
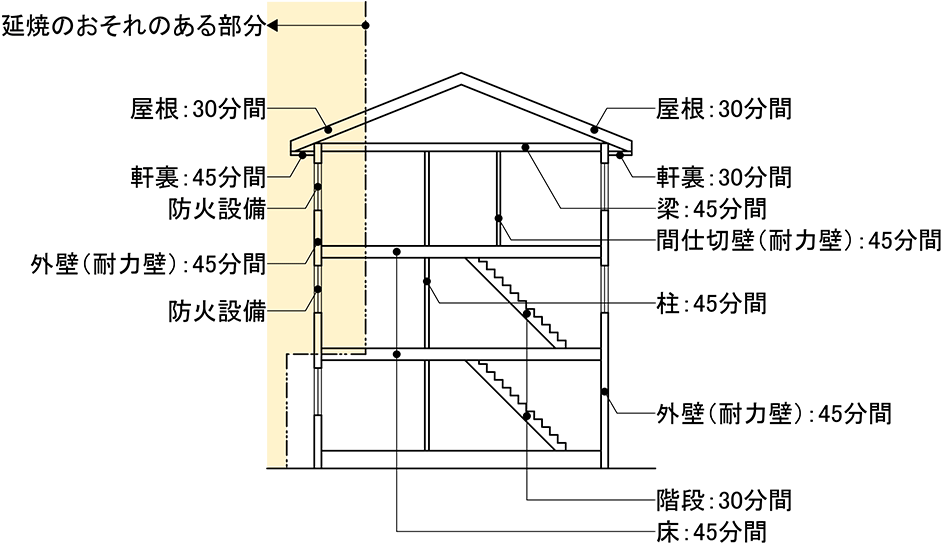
��2.��������-1���������������Ѳй�¤�ʷ��۴��ˡ�ܹ�����109���3��1���
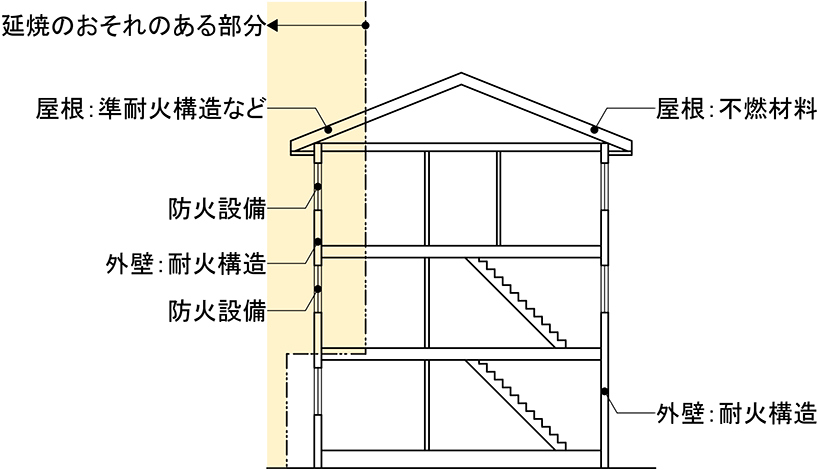
��3.��������-2��������������¤����dz�����ʷ��۴��ˡ�ܹ�����109���3��2���
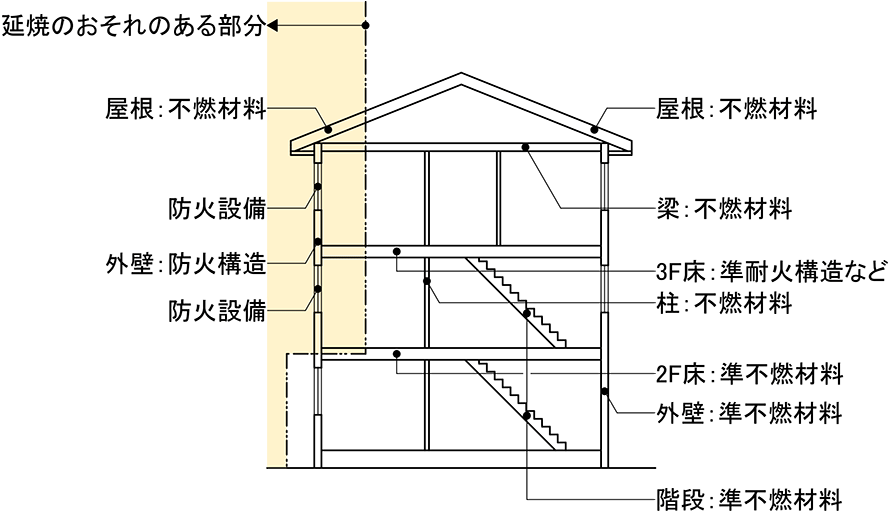
�ɲо���פʲ�������ʬ�λ��Ǥ���
|
����¤���Ȥʤ���ʬ |
�����������ʬ |
|
���� |
�� |
|
�� |
���� |
|
�� |
��¤���Ͼ���פǤʤ��ֻ����� |
|
�� |
��¤���Ͼ���פǤʤ����졢�դ��� |
|
���� |
����Ū�ʾ����ʡ��������� |
|
�� |
�夲�����Dz����ξ� |
���϶�������ƻϩ�濴����Ʊ���������2�ʾ�η���ʪ��ߤγ��ɴ֤��濴���顢1���ˤĤ��Ƥ�3�����⡢2
���ʾ�ˤĤ��Ƥ�5������ε�Υ�ˤ������ʪ����ʬ�Ǥ���
����������
����ʪ��ߤα�����Ѥι�פ�500�ְ���ξ��ϡ�1�η���ʪ�Ȥߤʤ��ޤ���
�ɲо�ͭ���ʸ��ࡢ���졢��ʤɤζ��Ϥ⤷���Ͽ��������Ѳй�¤���ɤʤɤ��̤�����Ͻ����ޤ���
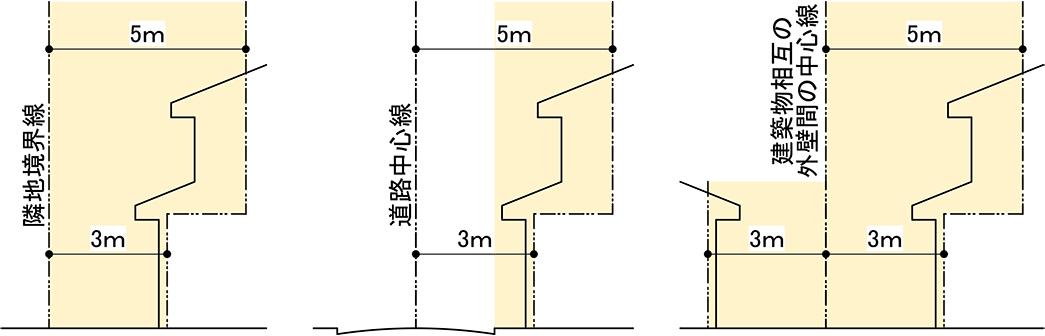
E-012. �ʽ���Ѳй�¤���ʽ���ɲй�¤�Ȥ�
�����Ѳй�¤
�ɲ��ϰ����3�����Ƹͷ��ƽ��������оݤȤʤ�ޤ���
�̾�βкҤˤ���Ǯ��ɽ�ˤ�������ֲä���줿���ˡ���¤���Ͼ�پ�Τ����ѷ��ʤɤ�»��������
�����ʤ���ΤǤ���
��ɽ�ι�ʿ��12ǯ���߾ʹ���1399��ˤˤ��Ŭ����Ͱʳ��ˡ����ڸ�����ä�ǧ�ꤷ����Τ�Ŭ��
���ޤ���
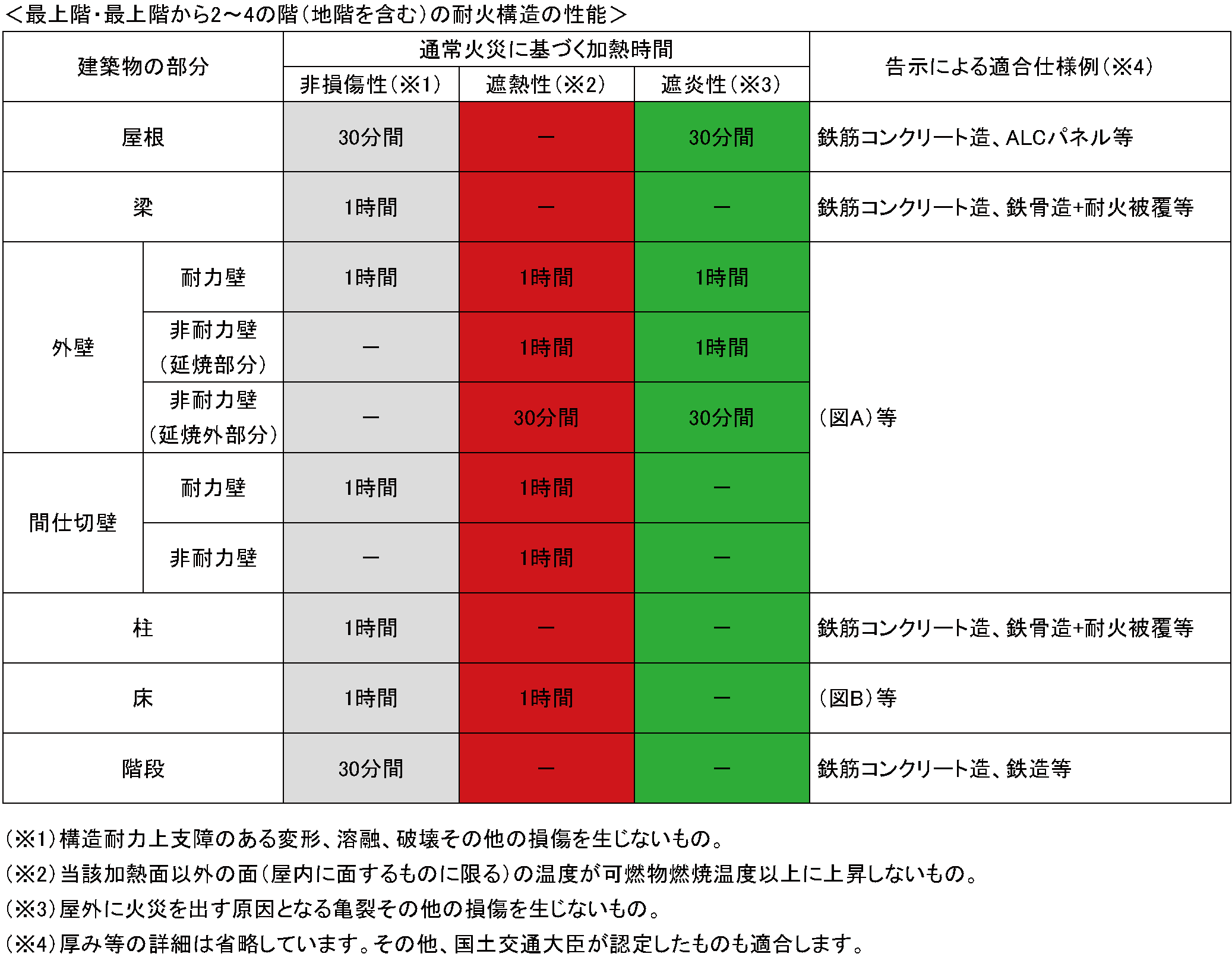
���ʿ�A�ˡ����ɵڤӴֻ����ɡ�1�����ѲСˤ��㡡
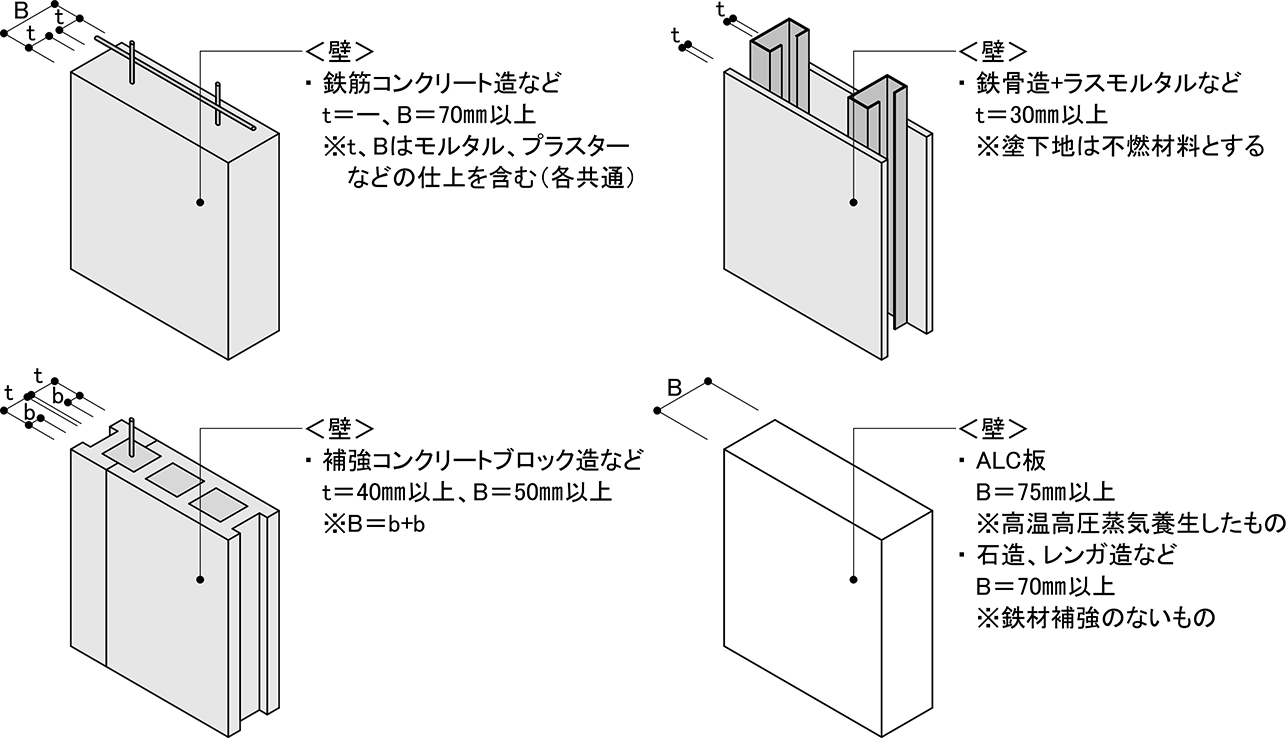
���ʿ�B�ˡ�����1�����ѲСˤ���
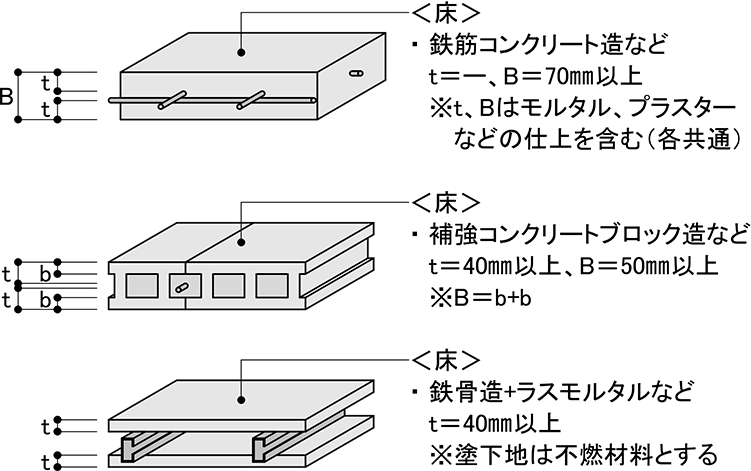
�������Ѳй�¤
���ɲ��ϰ����3�����Ƹͷ��ƽ��������оݤȤʤ�ޤ���
�̾�βкҤˤ���Ǯ��ɽ�ˤ�������ֲä���줿���ˡ���¤���Ͼ�پ�Τ����ѷ��ʤɤ�»��������
�����ʤ���ΤǤ���
��ɽ�ι�ʿ��12ǯ���߾ʹ���1358��ˤˤ��Ŭ����Ͱʳ��ˡ����ڸ�����ä�ǧ�ꤷ����Τ�Ŭ��
���ޤ���
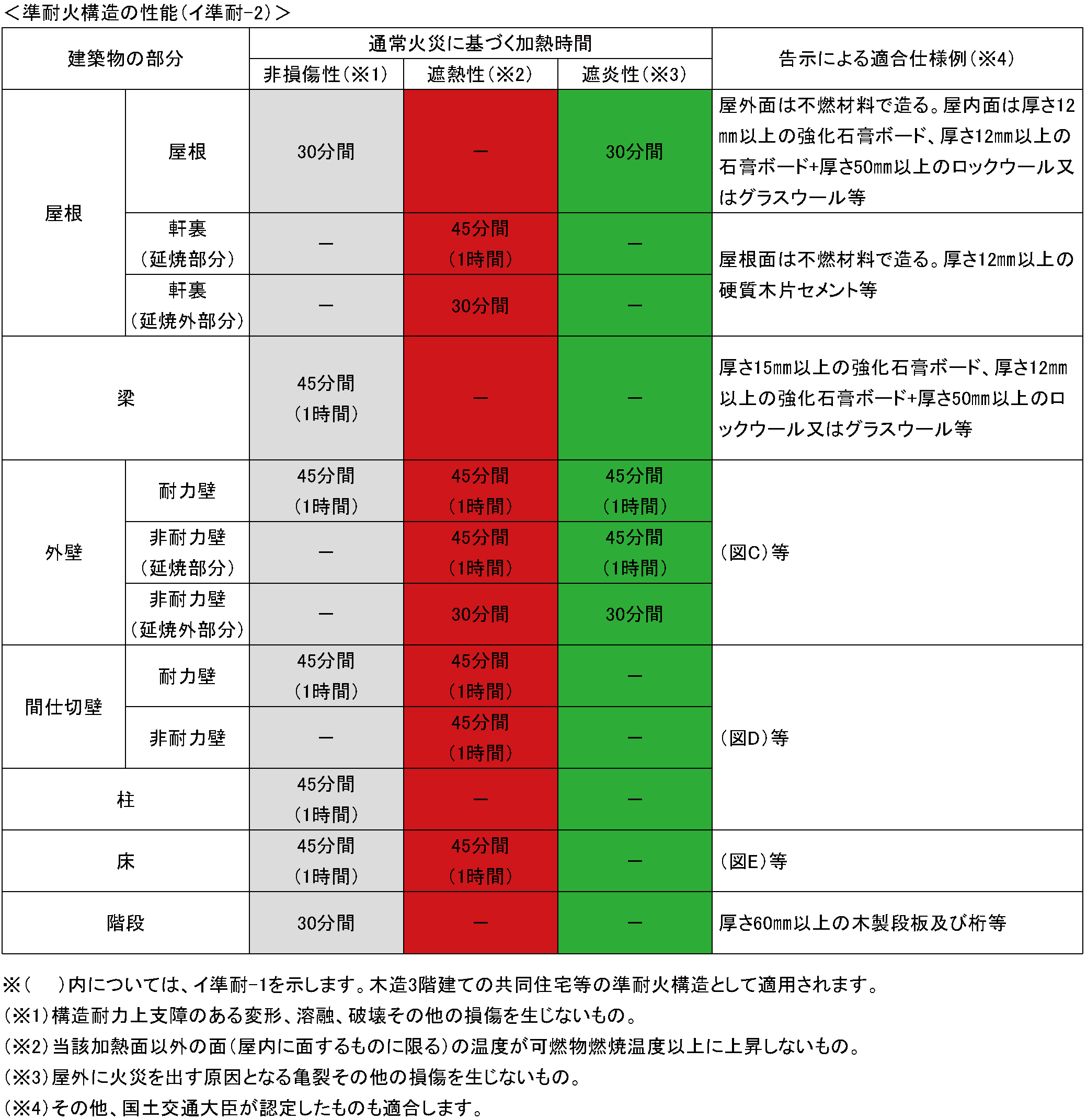
���ʢ��ˡ�E-009. �Ѳз���ʪ�����Ѳз���ʪ�Ȥ���1.�����Ѥ���ˡ��Ƥ��ޤ��Τǡ��������
���Ʋ�������
���ʿ�C�ˡ����ɡ�45ʬ���ѲСˤ���
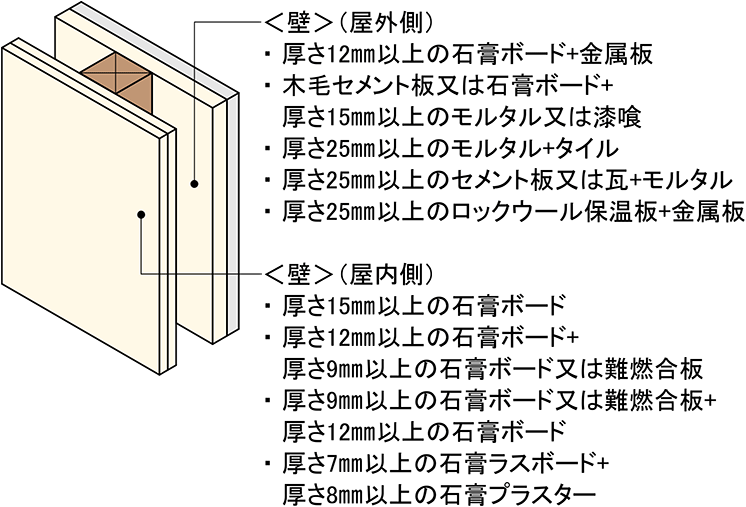
���ʿ�D�ˡ��ֻ����ɡ�45ʬ���ѲСˤ���
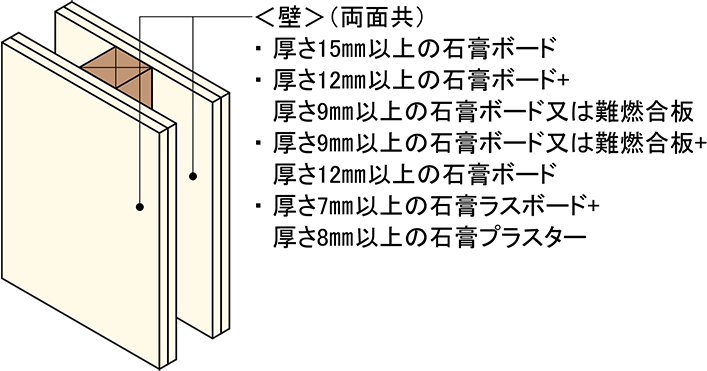
���ʿ�E�ˡ�����45ʬ���ѲСˤ���
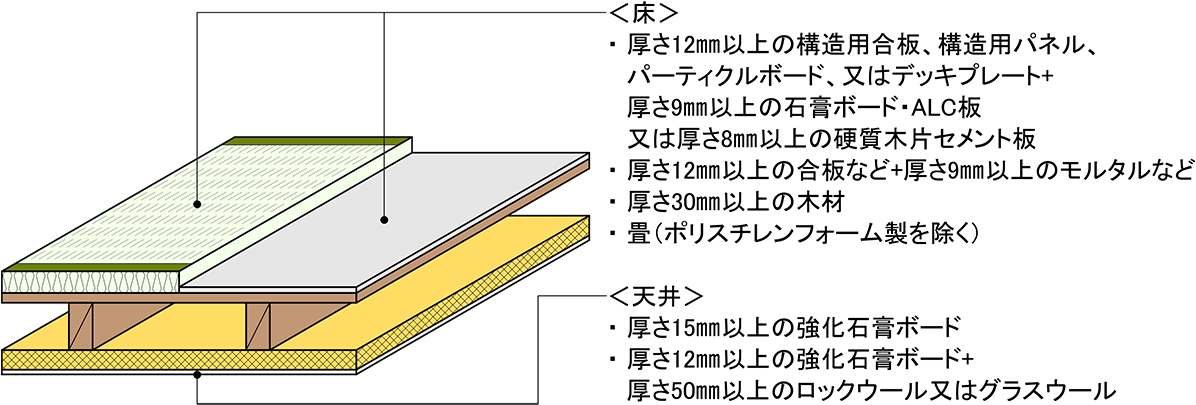
�����ɲй�¤
���ɲ��ϰ���DZ�ƤΤ�����Τ�����ʬ��1��2�����Ƹͷ��ƽ��������оݤˤʤ�ޤ���
Ŵ�ڥ����¤��Ŵ��¤����Ӥ����dz���䤹����¤����ʪ����դβкҤ�����٤�����줿��Τ�
�����ɤȸ��Τߤ˵��ꤵ�줿��¤�Ǥ���
��ɽ�ι�ʿ��12ǯ���߾ʹ���1359��ˤˤ��Ŭ����Ͱʳ��ˡ����ڸ�����ä�ǧ�ꤷ����Τ�Ŭ��
���ޤ���
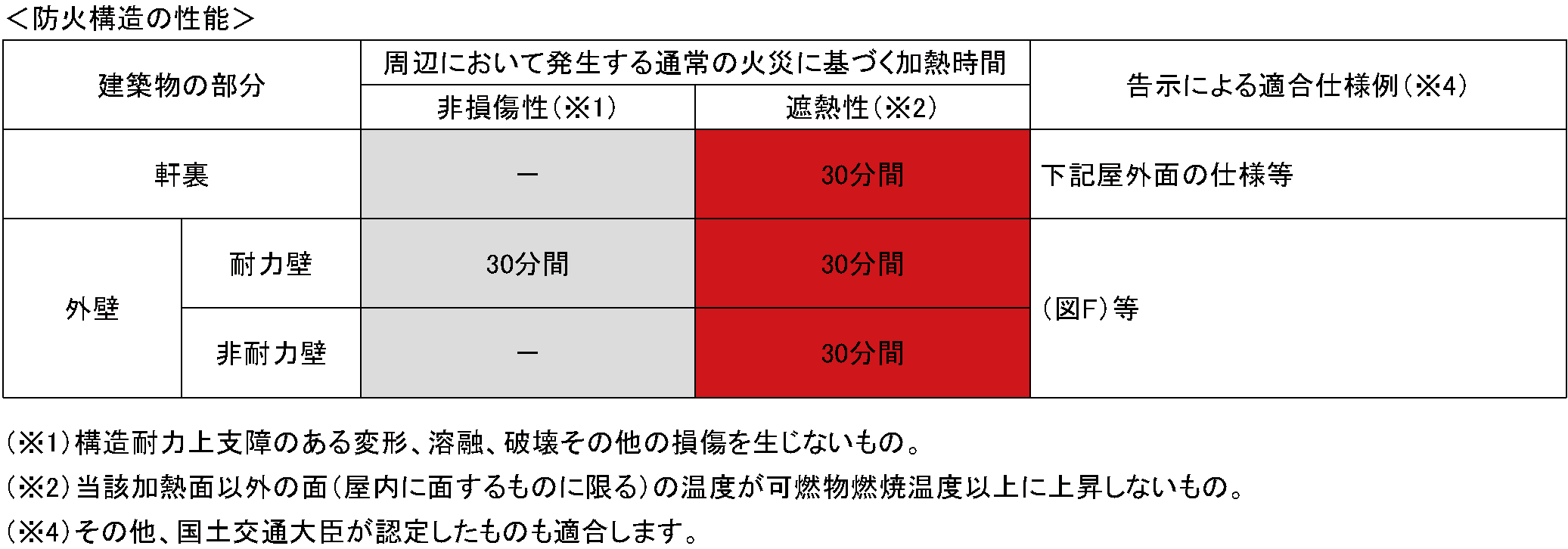
���ʿ�F�ˡ����ɡ������ɡ��������ɶ��̡ˤ���
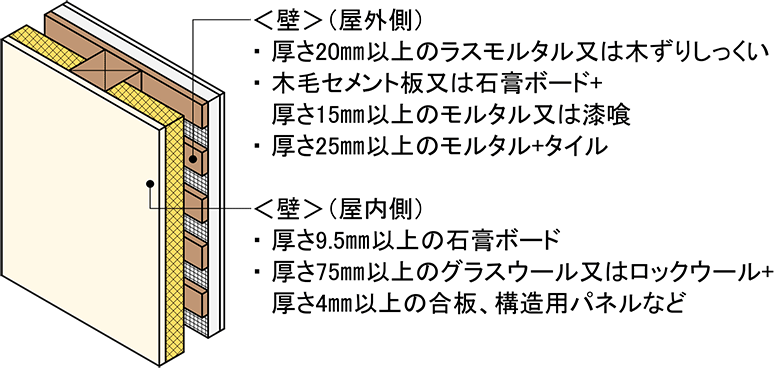
�������ɲй�¤
ˡ22������DZ�ƤΤ�����Τ�����ʬ��1��3�����Ƹͷ��ƽ��������оݤˤʤ�ޤ���
�����ɤ�Ʊ������ǽ����ä����ɹ�¤�Ǥ���
�ˤ��Ŭ����ͤϤ���ޤ������ڸ�����ä�ǧ�ꤷ����Τ�Ŭ�礷�ޤ���

E-013. ��dz����������dz��������dz�����Ȥ�
�̾�βкҤˤ���Ǯ���ä���줿���Ρ���dz��ǽ��ͭ���֤ˤ�äơ���dz����������dz��������dz������
��ʬ����Ƥ��ޤ���
���������ʬ����dz��ǽ��ͭ���֡�
|
������ʬ |
��dz��ǽ�ʢ�����ͭ���� |
Ŭ�Ѻ����� |
|
��dz���� |
20ʬ�� |
����ȡ����������륿�롢���ä������С�ƫ����������롢Ŵ������ߥ˥��ࡢ����12�аʾ���йѥܡ��ɤʤ� |
|
����dz���� |
10ʬ�� |
����9�аʾ���йѥܡ��ɡ�����15�аʾ�����ӥ����Ȥʤ� ����dz������ޤ� |
|
��dz���� |
5ʬ�� |
����5.5�аʾ����dz���ġ�����7�аʾ���йѥܡ��ɤʤ� ����dz����������dz������ޤ� |
��
���ʢ��ˡ���dz��ǽ
�����������������ǽ�Ǥ���
��1.��dz�Ƥ��ʤ���ΤǤ��뤳�ȡ���dz�����ˡ�
��2.���ɲо�ͭ�����ѷ�����ͻ����������¾��»���������ʤ���ΤǤ��뤳�ȡ���»�����ˡ�
��3.�������ͭ���ʱ����ϥ�����ȯ�����ʤ���ΤǤ��뤳�ȡ���ȯ�����ˡ���
����ʪ�������Ϥ����פ��ܤ�����֤�ʿ�Ѥι⤵�ˤ������ʿ�̤������̡�ʿ�������̡ˤȸ����ޤ���
�ְ㤤�䤹���ΤǤ��������Ϥ�ʿ�Ѥι⤵�ǤϤ���ޤ���
���㺹��3����Ķ������ϡ����㺹3�����⤴�Ȥ�ʿ�Ѥι⤵�ˤ������ʿ�̤Ǥ���
��äơ�Ʊ�����ϤǤ����ʪ�ΰ��֤ˤ�äơ������̤ι⤵���ۤʤ��礬����ޤ���
�����̤ϡ��ʷ��۴��ˡ�ˤ�����˷���ʪ�ι⤵�ε������Ȥʤ���פʤ�ΤǤ�����
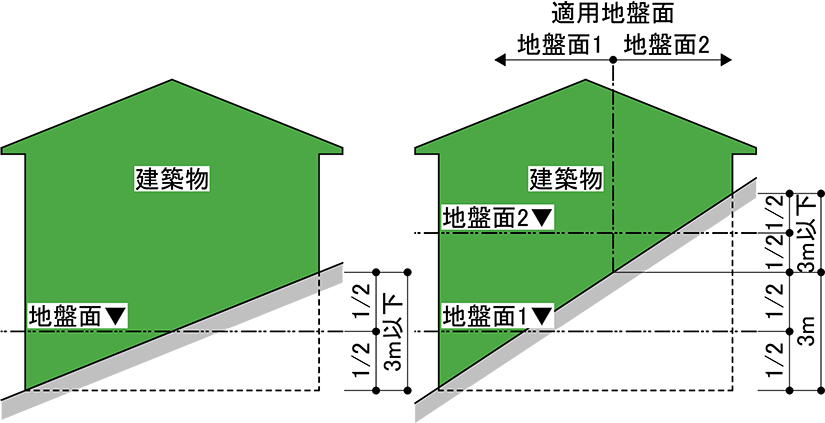
���������̲��ˤ��ꡢŷ��ι⤵��H�ˤ�1/3���������̤������⤤�����ϳ��ȸ����ޤ���
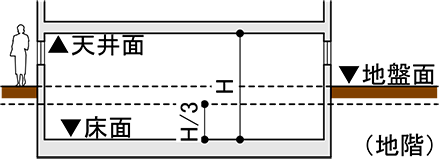
�サ����̳����ȡ�����ڡ�����¾�������ह����Ū�ΰ٤˷�³Ū�˻��Ѥ��뼼��\�ȸ����ޤ���
|
���� |
�\ |
�\�ʳ� |
|
���� |
��ӥ������˥���������ؤʤ� |
���ء�ϭ�����Ἴ�����̡�æ�Ἴ��ʪ�֡�Ǽ�͡������������������åȤʤ� |
|
�ع� |
���̶��������ڼ��������ʼ������ʼ����ΰ鼼���������ʤ� |
ϭ�����Ҹˡ��Ѷ�ˤʤ� |
|
��̳�� |
��̳������ļ������ܼ��ʤ� |
ϭ�����Ҹˡ���ʨ�������Ἴ�ʤ� |
|
����¾ |
��Ʊ����δ�����̳��������Ź�ο�˼��Ź�ޤ���졢����κ�ȼ�����������æ�Ἴ���Ἴ�ʤ� |
ϭ�����Ҹˡ����Ἴ�ʤ� |
�������ģ�Ȥϡ����ۼ�����֤���Į¼�ϻ�Į¼Ĺ������¾�ζ��Ǥ���ƻ�ܸ��λ��λ��Ǥ���
��ǧ����������Ȥʤ�ޤ���
��
���ۼ���Ȥϡ����۳�ǧ����λ��������Ԥ����¤��ĸ�̳���λ��Ǥ���
��ƻ�ܸ�������ǻ��ꤵ����25���Ͱʾ�λԤ��֤��졢����ʳ��λԶ�Į¼�ϡ�Ǥ�դ����֤���ޤ���
